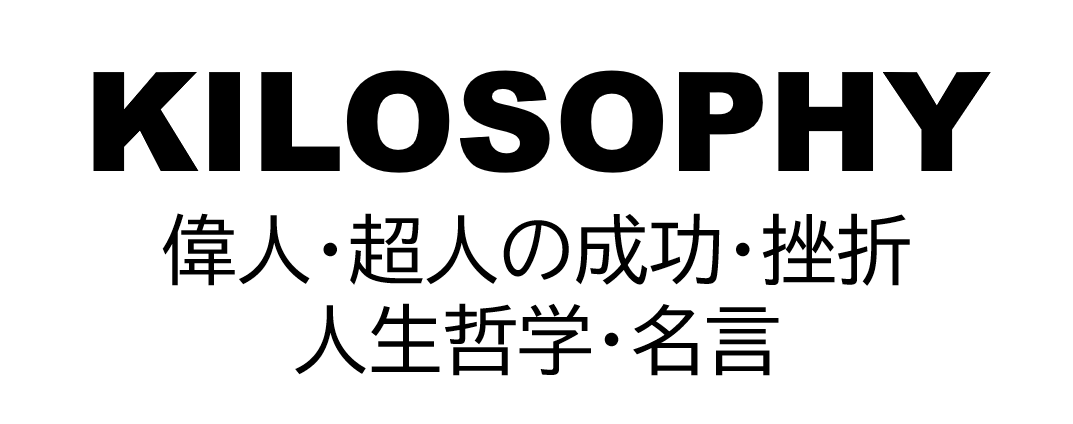セブン-イレブンを日本に持ち込み、やがてセブン&アイホールディングスという一大流通チェーンを作り上げた鈴木敏文。しかし彼の道は順風満帆ではなく、さまざまな転機、挫折に彩られてきた。そんな彼の人生の岐路を振り返る。
幼少期
誕生
- 1932年、長野県埴科郡坂城町で地主の父甚四郎、母比サ美の間に生まれた。父甚四郎は慶應出の元ジャーナリストで、鈴木が生まれた頃からは農協の組合長や町長などのの公職についていた。
少年時代 5人の姉からかわいがられて育つ
- 鈴木は9番目の子供であったため、兄弟に「敏ちゃん」と言われてかわいがられて育った。また、上に姉が5人続いて生まれた男の子だったため、父甚之助からもかわいがれた。母比サ美の躾は厳しかったが、面倒見のいい姉たちに囲まれて育ったことが、鈴木を楽天的な性格にした一因だった。
学生時代
13歳頃 あがり症で中学受験に失敗し、蚕業学校へ
- 小学校の成績は悪くなかった鈴木であったが、当時極度のあがり症で、旧制上田中学の受験に失敗してしまった。面接官に質問されても、何も答えることができず、小学校の高等科に1年通ったが、終戦で実業学校で手に職をつけたほうがいいとの両親の勧めにより、1946年、小県蚕業学校に入学した。
- 蚕業学校では、あがり症を治そうと弁論部に入部した。猛練習により上田地区の弁論大会で入賞できたが、その時でさえ、客席のほうを向くことができず、窓の外の梅の木を眺めていた。
- 小県蚕業学校は、終戦とともに高校になり、鈴木はこの学校に6年間在籍した。弁論部を通じて徐々に人前で話せるようになっていた鈴木は、周囲からの推薦もあり生徒会長を務めた。
- また、もともと足が遅いことがコンプレックスだったが、陸上部に入り猛練習したところ、短距離で県大会に出場するまでになった。
- このように、鈴木は蚕業学校を通じて、自分の至らない点と向き合い、克服していくという成長過程を通って行った。
19歳頃 実業学校から苦心の末、中央大学経済学部に入学
- 農協組合長や町長を務めた父の元には、井出市太郎などの政治家も出入りした。影響を受けた鈴木は、東京にある中央大学に進みたいと考えるようになった。しかし、鈴木が通う蚕業学校は、受験科目の授業がが少ないうえに、蚕のエサである桑の面倒も頻繁に見なければならなかった。いわば二足のわらじの苦労も乗り越え、鈴木は1952年に中央大学経済学部に入学した。
- 中央大学では、漠然と政治家を志し、国会を傍聴したり、父を通じて知り合ったの議員の事務所に出入りしたりしていた。しかしやがて大学の先輩から請われ、全学自治会に入会すると、大学2年生の時にたちまち書記長になってしまった。
- しかし親からは学生運動をするなら仕送りを止めると言われたため、書記長を退き調整役に徹したため、学生時代は「黒幕」というあだ名がついていた。
新社会人時代
23歳頃 全く希望していなかった東京出版販売に入社、マーケティングサイエンスに出会う
- 学生運動をやっていた鈴木は、大半の企業で敬遠される存在だった。そのため、学生運動に比較的寛容なマスコミの入社試験を受けたが、面接で失敗。結局、父親のつてを頼って入社試験を受けさせてもらい、1956年、全く希望していなかった東京出版販売に入社することになった。
- 最初の配属は本の返品係だった。返品されてくる出版科学研究所。東販が出版業の近代化のために設立した近代的な組織だった。そこで鈴木は消費者調査と、その分析手法としての統計学を一生懸命学んだ。図らずもこの経験をしたことが、後年の「データ経営」に結びついていく。
イトーヨーカ堂時代
29歳頃 独立のための出資を募るつもりで訪ねたイトーヨーカ堂に入社
- 出版科学研究所で3年間調査活動を行った後、鈴木は弘報課に異動し、広報誌を制作販売する業務についた。そうして色々な作家や著名人に会ううちに、評論家大宅壮一の門下生と共にテレビ番組制作プロダクションを設立する話が持ち上がった。
- あまり深く考えず、以前一度転職の面接を受けに行ったヨーカ堂にスポンサーになってくれるよう依頼に行くと、本部長は面白いといい、どうせならヨーカ堂に入社して実現したらどうだと言ってくれた。
すっかりその気になった鈴木は意気揚々ヨーカ堂に入社したが、実はヨーカ堂側にその気はなく、独立プロダクションの設立は全くすることができなかった。 - しかし親族の反対を押し切ってまで入社した経緯もあり、鈴木はヨーカ堂をやめるわけにはいかなかった。
「「そのヨーカ堂て何の会社だ。スーパーって何だ」私はヨーカ堂の名前はおろか、総合スーパーという業種についても知らなかったほど、流通業にはまったく関心がなかった。
(「挑戦 わがロマン 私の履歴書」鈴木敏文、2008年、日本経済新聞出版社)
32歳頃 人事課長として採用、人事制度構築に奔走
- ヨーカ堂に入社して商品管理課の係長として、納品の管理を任された。しかし販促担当が辞職してしまったことで、1か月後には販促に回された。
- 販促を経験した後は、どんどん人が辞めてしまう人事課長を兼務させられた。当時はヨーカ堂の認知度がそれほど高くなく、「スーパー」という業態も世間に認知されていなかった。そこで鈴木は、当時最新式のスライド機材を持って全国の高校を回り、言葉ではなく映像でヨーカ堂の会社説明をしたり、親しみを持て貰えるよう女性リクルーターを使うなどの工夫を行っていた。
- ヨーカ堂の成長と共に毎年の新卒採用人数は増え続け、自動車などの花形産業と人材を争うようになった。そこで鈴木は交渉の末、1970年には旺文社の受験雑誌「蛍雪時代」とタイアップした高校生喧噪作文コンクールを実施した。コンクールの送品はハワイ研修旅行で好評を博し、ヨーカ堂の知名度向上に貢献した。
39歳頃 取締役としてヨーカ堂の東証二部上場を推進
- 1938年、鈴木はそれまでの貢献が認められ、ヨーカ堂の取締役に昇進した。
- 当時ヨーカ堂は急速に店舗網を拡大させており、資金調達の必要性が高まっていた。伊藤社長をはじめとして社員、メインバンクが難色を示す中、鈴木は根気強く説得を続け、1939年、ついにヨーカ堂は東証二部に上場した。
39歳頃 セブン-イレブンとの出会い
- 1960年代の高度成長期あたりから、小型店の生産性が低下し、ヨーカ堂が進出しようとすると、地元商店街から強い反発を受け、進出が思うように進まなくなった。大型店と小型店の共存共栄は不可能で、大型店は小型店を潰す外的だと見なされた。
- 鈴木氏は商店街を説得するために、代替案を探した。ある日米国視察に行くと、大型店がひしめく米国にあって、成功している小型店セブン-イレブンを発見した。セブン-イレブンは小型店ながら効率的な経営をしており、運営企業のサウスランド社は4000店ものチェーンを経営していた。「このような小型店ならば、日本の大型店とも共存できる」-そう直感した鈴木は、セブン-イレブンの導入を計画した。
セブンイレブン時代
40歳頃 ヨークジャパン設立、サウスランド社とライセンス契約を締結
- 社内外からは反対の声一色だった。人事、販促、広報といった管理畑を歩み、販売経験のなかった鈴木は「夢物語」とまで言われたが、セブン-イレブンの導入を諦めなかった。
- しかし世界最大のコンビニチェーンのサウスランド社との交渉は難航した。高度経済成長中とは言え、当時の日本はまだ成果の一流国ではなく、ヨーカ堂は国内の小売業界で15位の中堅企業に過ぎなかった。サウスランド社は、「展開エリアは東日本のみ」「8年間で2千店出店」「ロイヤルティは売上の1%」という厳しい注文を付けてきた。鈴木は交渉の最前線に立ち、時にはテーブルを叩き粘り強く交渉し、「展開エリアは日本全域」「8年間で1200店出店」「ロイヤルティは売上の0.6%」という条件でライセンス契約にこぎつけた。
- 契約とほぼ同時期に、ヨークセブン(後のセブン-イレブンジャパン)を設立した。資本金は1億円で、鈴木を含む4人が貯金や借り入れを使ってなんとか工面した。
ヨークセブンの社員は15人で、イトーヨーカ堂からの転籍者と、新規募集で集めたが、殆どが小売業界での経験がない、素人集団だった。
41歳頃 セブン-イレブン1号店を東京都江東区豊洲にオープン
- 当初は、世界最大のコンビニチェーンであるサウスランド社から、店舗運営ノウハウを学び、それを元に事業を始める予定だった。
- しかし、米国サウスランド社にヨークジャパンの社員と共に研修に出かけても、得られるものは殆どなかった。商品政策や物流に関するノウハウはなく、冷凍ハンバーガーを店舗で温めるだけ、といった有様だった。鈴木はがく然としながらも、すべてを自力でやる決意を新たにした。
- 新聞に広告を載せると、豊洲の酒屋から開店したいとの手紙が来て、早速会いに行った。若い店主の熱意に引かれた鈴木は、この酒屋を1号店とすることを決めた。
- 3か月という限られたスケジュールの中、店舗を改装し、3000品目以上に上る商品の選定、冷蔵庫の改造といったことをしていった。当時まだまだ「素人集団」であったヨークセブンにとっては初めてのことだらけだったが、無事開店までこぎつけることができた。
43歳頃 ドミナント戦略を展開しながらセブン-イレブン100店舗を達成
- 豊洲の一号店のオープン1か月後、鈴木は意外な知らせを聞いた。酒屋からコンビニに変えて、日販は倍増していたものの、利益は殆ど増えていないというものだった。原因は、在庫が積みあがっていたことだった。
- 当時の商慣習では、あらゆる商品を大ロットで仕入れすることが前提となっていた。そのため、売れない商品は大量の在庫が残り、売れる商品も、売り場の制約などの理由から利益が制約されていた。
- 当時の商慣習では考えられないことであったが、鈴木は仕入れ問屋に小口配送をしてもらうよう交渉し、徹底して店舗同士を近接させるドミナント戦略をとることで、小口配送を実現した。これによって、需要に応じた仕入れができるようになり、店舗の収益安定化に貢献した。
45歳頃 セブン-イレブンで業界初のおにぎりを発売
- セブン-イレブンでは当初、米国で取り扱っていたファストフードを販売していたが、日本の消費者が求める品質に達していなかった。例えば、ホットドッグを保温機に入れて販売していたが、長時間時間が経過し皮が乾いてしまったものに日本の消費者は手を出さなかった。
- そこで鈴木は、日本ならではのファストフードとしておにぎりを考案し、1976年に開発をスタートさせた。今でこそコンビニに当たり前のように並んでいるおにぎりだが、家庭で作れることを理由に、当時は社内で反対意見が多かった。
- しかし鈴木は、おにぎりは日本人の誰もが食べるもので潜在需要が大きいと考え、開発を推し進めた。すると、2年後には海苔をフィルムで包み、食べるときにご飯とまくことで新鮮な食感を味わえる「パリッとフィルム」を考案した。家庭で握ったおにぎりと差別化ができた瞬間だった。セブン-イレブンのおにぎりは大ブレイク商品となった。
46歳頃 史上最短の設立6年目で東証二部上場
- 1978年、500店舗を達成すると、1979年には史上最短となる設立6年目で東証二部に上場した。
- もっとも、史上最短記録を狙って6年目に上場したわけではなかった。親会社のイトーヨーカー堂は自社の出店で資金繰りが手一杯であり、イトーヨーカ堂の反対を押し切って事業を始めた経緯もあったため、財務基盤を親会社に頼るわけにいかなかったという背景があった。
50歳頃 セブン-イレブン、日本初の本格的POSを全店舗に導入
- セブン-イレブンでは、1978年時点で、全店に発注端末機であるターミナルセブンを導入していた。これは発注の際に、発注台帳から品目をバーコードで読み取れば、それで発注できるという当時最新のシステムだった。
- しかし、発注のデータだけでは、その後実際に商品がいつ、どれくらい売れたのかがわからない。そこで、1983年、鈴木はセブン-イレブンに日本初となる本格的なPOSシステムを全店舗に導入した。
- 構想自体はその前から持っていたが、POSデータがあることで、現場の人間がデータだけに捕らわれることをおそれて自分で考えなくなる弊害をおそれ、敢えて導入を遅らせていた。商品ごとに需要がどれくらいか仮説を立て、POSを通じて検証するという「単品管理」の考え方を店舗オーナーやアルバイトに浸透させてから、一気に導入した。
58歳頃 サウスランド社の株式を取得し経営再建を開始
- 1990年、米国のサウスランド社から急遽、支援要請が入った。原因は、本業の低迷と、1980年代からの多角化が失敗したことであった。1980年代の米国では、大型店も24時間化を進めるとともに、値引き攻勢をしかけてきた。コンビニは価格競争に巻き込まれ、収益率がみるみる低下していった。さらに、サウスランド社は不動産事業、石油精製事業に手を広げていたが、80年代半ばの石油価格暴落、宇宙開発凍結に伴う不動産価格暴落が追い打ちをかけ、日本側に救済を求めてきたのであった。
- コンビニ終焉説も囁かれたが、鈴木は変化に対応できる仕組みに作り直せば十分に経営は成り立つと考え、1991年、サウスランド社の株式の70%を買収した。
- 買収すると、米国に自ら乗り込み、既存の経営の在り方を全て否定し、効率的な仕組みに変えていった。そのため、現地では渡米の度に全てを破壊していく「ハリケーンスズキ」と呼ばれた。
- サウスランド社の経営で問題になっていたのは、自社保有していた物流センターだった。物流センターは自らの個別最適=大量発注による買い付け単価削減を追求する結果、商品の需要と関係なく大ロットでの商品発注をしてしまう。それによって店舗側では売れ筋商品の機会ロスと、大量の在庫廃棄というコストが生じる。それを看破した鈴木は、物流センターを卸売り企業に売却してしまった。
- さらにもう一つ大きな変革として、鈴木は発注権限を現場に委譲させた。サウスランド社では、店舗側に発注権限がなかった。物流センターや本部が買い付けた商品が届けられるか、商品のベンダーが定期的に店舗を回り、自社の都合で商品を並べていた。これでは顧客の需要に合致する商品をそろえることは到底できないと考えた鈴木は、パート従業員に教育を徹底した上でPOSシステムを導入して、品揃えを改善していった。
- そうして、3年目には黒字転換、10年目となる2000年にはニューヨーク証券取引所に再上場を果たした。
69歳頃 アイワイバンク(現セブン銀行)を設立
- 1987年にセブン-イレブンが公共料金などの収納代行サービスを始めると、利便性の高さから取り扱い額がどんどん増えていった。顧客は、銀行で公共料金を支払おうとすると、営業時間内にいかなければいけないが、コンビニならばいつでも支払えるためだった。
- 鈴木は当初都銀4行と構想を進めたが、共同運営方式では、コンビニは単に軒先を貸すだけの「大家」になってしまい、設置場所や手数料などの決定権を握れなった。
- 時を同じくして、日債銀の共同買収をソフトバンクなどから持ち掛けられたが、日債銀の子会社の日債銀信託のみが欲しかった鈴木は、買収を断念。
- 結局、小売企業が銀行を作るという前代未聞の判断を下し、1999年には銀行設立趣意書を金融庁に提出した。バブル崩壊後で銀行が潰れていく中での判断に、誰もが懐疑的だった。
- しかし鈴木は、当時1台800万円だったATMを、メーカーと一緒に不要な機能を削減していき、1台200万円で調達できるようにした。また、ATMへの現金の搬送補充、点検業務も警備会社に委託することで徹底したローコストオペレーションを実現した。
- その結果、当初2年間は赤字だったが、3年目に十分な設置台数が稼げると、黒字化に成功した。
71歳頃 2年間の準備期間を経て、北京にセブン-イレブンを出店
- 1990年代半ば、中国政府から、流通の近代化のためにセブン-イレブンに出店してほしいとの要望を受けた。しかし物流などのインフラが整備されていなかったため、まずは店舗である程度の機能を備えているイトーヨーカドーが出店した。
- イトーヨーカ堂で中国人店長の登用、幹部社員育成など現地化を勧めノウハウを蓄えた後、満を持して2002年からセブン-イレブン北京一号店の出店準備に取り掛かった。しかし異国でのビジネスは事業環境が異なることから、苦労の連続だった。
- 北京ではメーカーが直接納入する形態になっており、一日に70台もの車両が納入に入ってくる状態だった。それをセブン-イレブン側がメーカーと粘り強く交渉して混載などをさせ、日本と同じ1日10台体制の納入まで整理した。
- また、食の現地化にも取り組まなければならなかった。中国は日本より外食文化が発達しており、安くておいしい外食がそこら中にある。それに対抗するため、店舗での調理を実施した。しかし店舗での調理は品質のばらつきと表裏一体である。そのため、一年半かけて、材料をあらかじめカットし、調味料も整え、店舗では加熱調理をするだけで料理が完成する仕組みを作り上げた。
- こうした苦労を乗り越え、2004年に北京セブン-イレブンの1号店をオープンし、大成功を収めた。
73歳頃 セブン&アイホールディングスを設立し、巨大流通チェーンに進化
- セブン-イレブンは短期間に日本での売り上げ1位のコンビニチェーンとして大きく成長し、親会社だったイトーヨーカ堂の時価総額を大きく上回ってしまっていた。
- このねじれを解消するため、鈴木はセブン&アイホールディングスを持株会社として各社がその下にぶらさがる形に組織を再編した。
- また、このことが呼び水となり、当時西武とそごうを再編していたミレニアムホールディングス、東北で圧倒的シェアを誇る小売りチェーンヨークベニマルも子会社化し、セブン&アイホールディングスは巨大流通チェーンになった。