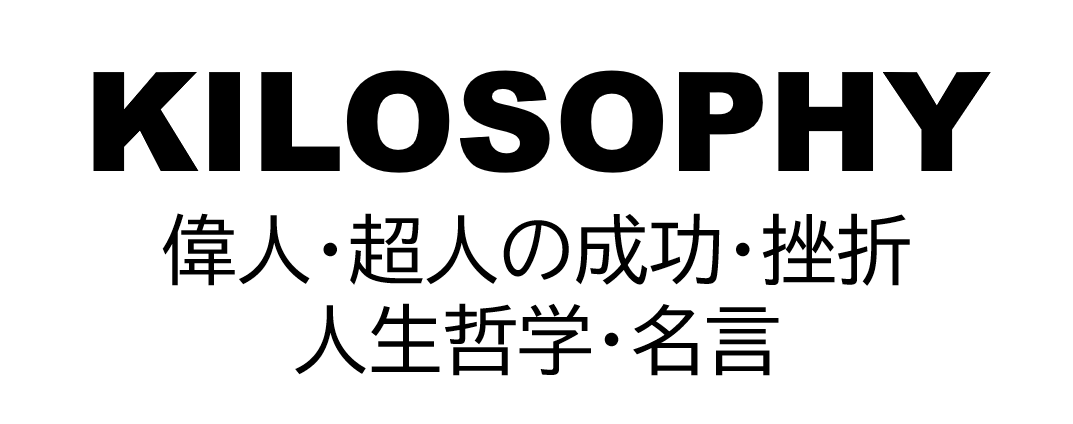自動車修理工から身を起こし、「世界のホンダ」を一代で築いた本田宗一郎。彼がどのような人生を歩んできたのか、人生の岐路を振り返る。
幼少時代
0歳 宗一郎、誕生
- 宗一郎は、1906年に静岡県磐田郡光明村で鍛冶屋を営む父儀平と母みかの間に長男として生まれた。
3歳頃 鍛冶屋の父親の仕事場に出入り
- 父儀平は包丁や農具、日本刀などを作っており、宗一郎は職人として働く父を見ながら育った。
- 3歳の時には宗一郎は父親の仕事場に入り、自分で好き勝手に何か物を作っており、4、5歳の時点では既に父親の仕事を手伝っていた。
- この頃、光明村では、当時珍しかった原動機で動く精米機があった。また、林業が盛んな光明村の製材所では電気モーターで動く丸ノコギリがあり、宗一郎はこうした機械を見るのが好きだった。
- また、この頃光明村に初めて電気が通り、電灯がついた。電気工事夫がペンチやドライバーをぶら下げて電柱に上り、電線をひねる姿を見て、宗一郎はそのかっこよさに感激した。
- この頃から既に宗一郎は、機械に大きな興味を抱いていた。
学生時代
6歳頃 光明村立山東尋常小学校入学
- 宗一郎は、機械や物をいじるのが得意だったが、文字を読んだり書いたりすることが苦手で、そのため学校の成績は唱歌を除いていつも悪かった。
- そんな宗一郎はいたずら小僧だった。小学校の裏山にあるすいか畑畑に忍び込み、すいかに穴をあけ、中身だけきれいに食べて逃げていた。また、自分のお腹が空いたために村中が昼食の基準としていた清海寺の鐘を勝手に鳴らしていた。
- 宗一郎は在校中に、初めて自動車を見た。当時まだ珍しかった自動車が光明村にやってきた話を耳にして、宗一郎は車のもとへすっ飛んでいった。宗一郎は、低速で走る車の後ろにつかまり、一緒に走ったり、停車した車から滴り落ちるオイルのにおいをかぎながら、将来は自分も車を作ってみたいと思った。
- 宗一郎が5年生の頃、浜松の歩兵連隊に当時まだ珍しかった飛行機が来ており、飛行機ショーが行われることとなった。それを聞いた宗一郎は、学校をさぼり、家族から2銭をくすねて、自宅から20㎞離れた飛行機ショーに父親の自転車で向かった。
- しかしいざ着いてみると、入場料は10銭で、持っていった2銭では足りなかった。諦めきれない宗一郎は、近くの松の木を登って、ナイルス・スミス号の飛行を実際に見た。初めて見る飛行機に感激した宗一郎は、帰り道も自転車を漕いであっという間に家に帰った。父儀平は宗一郎の行動力にただ驚くばかりで、怒ることはなかった。この出来事から宗一郎は、自分で飛行機を作って飛ばしてみたいという思いを生涯持ち続けることとなり、のちのホンダジェットへとつながることになった。
- ちなみに、宗一郎が松の木に上って飛行機を見ていた時、後年宗一郎のかけがえのない友人となる、ソニー創業者・井深大も同じショーを見に来ていた。井深はその時祖父に連れられていたため、宗一郎よりも間近で飛行機を見ることができた。井深はこの違いが二人の飛行機への熱意への違いになったと後年、述懐している。
『子どものころ、ふたりとも同じ飛行機を見たわけですが、その後、本田さんはエンジンに関心を持ち、飛行機への関心を失わなかったのに対して、私のほうは、電気の分野に進んだのは、連れて行ってくれる人がいなくても、どうしても見たいという一心を捨てなかった本田さんと、多少”環境”に恵まれていて、飛行機に対する好奇心が、わりあい簡単に満たされてしまった私との違いからかもしれません。
…その後、生涯にわたる本田さんの飛行機への関心は、このとき、強く芽生えたのではないでしょうか』
(井深大(2015)「わが友本田宗一郎」ゴマブックス)
12歳頃 二俣町立尋常高等小学校入学
- 宗一郎は小学校を卒業すると、光明村の自宅から4km離れた、隣町の二俣町の高等小学校に通い始めた。
- 通学中、途中にある定食屋のサバの煮つけを見ては、早く大人になってお金を稼いで、腹いっぱいにサバの煮つけを食べたいと考えていた。
- また、宗一郎は父儀平から、山葉寅楠(ヤマハ創業者)など地元浜松出身の発明家の話を聞かされて育ったため、技術を身に付けて独立したいという思いをこの頃から持っていた。
- 宗一郎が高等小学校に在学中、父儀平は、鍛冶屋から転じて自転車販売店を開業した。鍛冶屋の傍ら、当時普及し始めていた自転車の修理を頼まれたのがきっかけだった。
- 儀平が東京から取り寄せる「輪業の世界」という雑誌を、宗一郎は読みふけっていた。
- ある時宗一郎が「輪業の世界」を読んでいると、「アート商会」という自動車の修理工場の求人広告を発見した。もともと自動車修理をやりたいと考えていた宗一郎はアート商会に手紙を書いた。
- すると、5日ほど経って、宗一郎を採用する旨の返事が届いた。母みかは跡取りを東京に出すことに反対したが、「これからは自動車の時代だ」という宗一郎の言葉に、父儀平は納得し、上京を許可した。宗一郎若干15歳の決断であった。
東京での修業時代
15歳頃 アート商会に自動車修理工として入社
- 父儀平の付き添いで上京した宗一郎は、東京の本郷湯島にあったアート商会に修理工として入社した。しかし、現実は理想とはかけ離れており、来る日も来る日も主人の赤ん坊の世話と、雑巾がけしかやらせてもらえなかった。
- 先輩たちの修理する姿を見ることさえできず、宗一郎は何度も故郷に帰りたい思いに駆られた。
「失望と情けなさに、私は何度柳行李をまとめ、二階からロープを伝って逃げようと思ったことか。そのたびに故郷のおやじの怒る顔と、おふくろの泣く姿が目に浮かんで決意が鈍った。」
(本田宗一郎(2001)「本田宗一郎 夢を力に」日本経済新聞出版社)
- アート商会に入社して半年ほど経った頃、ようやく宗一郎にチャンスが回ってきた。大雪の降った年の瀬のある日、あまりの忙しさに、宗一郎も手伝いを命じられた。
- 宗一郎は嬉しくてたまらず、無我夢中で自動車の下に潜り込み、ワイヤが切れたアンダーカバーを修理した。その甲斐あってアート商会の主人に褒められ、次第にさまざまな修理を任されるようになった。
- 父儀平の元で自転車の修理を手伝っていた宗一郎は、機械いじりの素養がみについていたのであろう。自動車の修理もみるみるうちに上達していった。
これが私が初めて自動車修理をしたときで、そのときの感激は一生忘れることができない。
(本田宗一郎(2001)「本田宗一郎 夢を力に」日本経済新聞出版社)
17歳頃 震災の最中、初めて自動車を運転15歳
- 宗一郎がアート商会に入社して1年半ほど経った1923年、関東大震災が発生した。
- 東京のあちこちで火事が発生していたため、運転できる社員は、客から預かっていた車を火が届かない場所まで退避させることを命じられた。
- 宗一郎はこの時免許も持っておらず、運転経験もなかったが、内心しめたと思い、兄弟子たちより先んじて車に乗り込んだ。
- 火事から逃げる群衆の中、宗一郎は、生まれて初めて車を運転する喜びに感激していた。
そのときの俺は、自分が自動車を運転しているのだ、という感激のほかは何も感じなかったよ。俺の人生の中で、こんな歴史的感動は最大のものだ。運転そのものはアクセルの要領なんかがわからず、危なっかしかったが、その歓喜は二度と味わえないものだった
(梶原一明(2009)「一冊でわかる!本田宗一郎」PHP研究所)
18歳頃 一人前の自動車修理工となる
- アート商会に入社して3年が経った頃、宗一郎は盛岡に1人で出張を命じられた。消防車を修理するという仕事だったが、宗一郎は一人で消防車の分解、修理、組み立てを行い、無事に試運転まで行った。その甲斐あって、消防車は故障前の性能を無事に取り戻した。その月末、宗一郎はついに主人から一人前の職人と認められ、初めて給料を渡された。
経営者になりたての時代
22歳頃 アート商会浜松支店を立ち上げ
- アート商会に入社して6年が経ち、自動車修理工として大きく活躍していた宗一郎は、ついに主人からのれんわけを許された。
- やがて宗一郎は、地元近くにアート商会浜松支店を立ち上げた。
- 宗一郎はまだ若造で従業員も1人しかいなかったが、「他店で直らないものが直る」と評判になり、1年目から事業は順調に進んだ。
- 既に自動車を熟知していた宗一郎は、25歳の時に、それまで木製だった自動車のスポークを鉄製にし、特許を取得した。この鉄製スポークを生産するメーカーが現れ、特許料収入が得られるようになったことで、宗一郎の事業はますます順調になった。
- 事業を始めた時、宗一郎は一生かかって千円貯めることを目標にしていたが、25歳になる頃には、毎月数千円を儲けるようになっていた。この頃の宗一郎は、外国製の自家用車を2台持ち、芸者を買って大いに遊んでいた。
29歳頃 妻さちと結婚
- 宗一郎は29歳の時、知人の紹介から、当時地元の小学校の教師だった、7歳年下の磯部さちとお見合いをした。さちは高等女学校を卒業したのち2年間の専修科も修了していた、教養のある女性だった。宗一郎はその波乱万丈の生涯を妻さちとともに歩んでいくこととなった。
ものづくりに挑戦し始めた時代
30歳頃 東海精機重工業株式会社を立ち上げ、ピストンリングの製造を開始
- 自動車修理業を順調に経営していた宗一郎だったが、ものづくりを本格的に始めることを決意した。自社で自動車修理工として雇っていた従業員が独立し始め、彼らと競合することが嫌だったことに加え、東京やアメリカと取引をするような大きな仕事がしたいと感じたのが理由だった。
- 当初はアート商会幹部から猛反発をくらい、心労がたたった宗一郎は顔面神経痛になり2か月も会社を休むことになった。しかし仲介者が幹部との仲をとりもってくれ、合意をとることができた。
- 宗一郎は東海精機重工業株式会社を設立すると、アート商会の倉庫に「アートピストンリング研究所」という看板を掲げ、ピストンリングの製造に着手した。
- ところが、工員50人と生産設備を用意して始まった東海精機重工業は、思うような製品を作ることができず、立ち上げ後すぐにピンチに陥った。
- 宗一郎は、毎日明け方まで研究に没頭した。髪もひげも伸び放題で、伸びた髪は、妻さちに来て切ってもらい、工場の炉のそばにムシロを引いて寝るという生活だった。
- アート商会時代は金にものを言わせて芸者と遊びつくした洒落者の宗一郎だったが、この頃は資金が底をつき、そんな余裕はなくなっていた。
- 宗一郎は、ピストンリングがうまく作れないのは、自分自分に鋳物の基礎的な知識が不足しているためだと考え、浜松工高(現静岡大学工学部)に聴講生として通い始めた。
- 宗一郎は、聴講生として得た金属材料や冶金の知識をピストンリングの開発にすぐに応用し、製作開始から9か月目にしてようやくピストンリングの製造に成功した。
「俺が今までいちばん仕事でうれしかったのは震災で自動車をはじめて運転したとき。いちばん苦しかったのが、ピストンリングの研究開発。俺だって世帯もちで学生服なんか着て学校に通うなんて、苦しくなきゃやらねぇよ。でも、そのおかげで今日があると思ってる。とにかく、そのときは、開発できなきゃ、膨大な負債を抱えて倒産だよ。俺だけならともかく、五〇人の従業員とその家族のことを思えば、なにがなんでも俺はやらなきゃならなかった」
(梶原一明(2009)「一冊でわかる!本田宗一郎」PHP研究所)
33歳頃 東海精機重工業の社長に就任
- 宗一郎はついにアート商会浜松支店を弟子に譲り、1939年には自ら東海精機重工業の社長に就任した。
- トヨタからピストンリング3万本の受注を貰い幸先良いスタートを切った。
- しかし、納品前の品質検査で、ピストンリング50本中47本が不合格となってしまった。東海精機にはまだ量産するだけの製造技術がなかったのである。
- そこで宗一郎は、全国各地の研究者や職人を訪ねて知識を蓄え、自ら試行錯誤することで製造技術を磨いていった。
- この間にピストンリング関連の特許を28件、それ以外も含めれば40件以上の特許を獲得し生産技術をわがものにした宗一郎は、2年経ってついにトヨタの納品前検査に合格することができた。
- ピストンリングの納入を契機にトヨタの資本金を受け入れ、東海精機重工業の資本金の40%をトヨタが持つことになった。その資金を元にピストンリングの生産を本格化させ、終戦までトヨタ向けだけでなく、海軍の船や、中島飛行機の航空機用のピストンリングも納入を続けた。
戦後、復活の時代
39歳頃 終戦とともに東海精機重工業の社長を退任、「人間休業」宣言
- 1945年に戦争が終わると、それまで東海精機重工業で製造していた軍事用のピストンリングは需要がなくなってしまった。
- トヨタ向けにピストンリングを製造するという選択肢もあったが、トヨタが派遣した監督官のと意見が合わず、さらにGHQによってトヨタが解散させられるという噂もあり、宗一郎は45万円で東海精機重工業の株式を全てトヨタに売り、完全に身を引いた。
- 終戦後1年間、宗一郎は「人間休業」宣言を行い、一切働かずに自由に過ごした。尺八を吹いたり将棋を指したり、当時非常に高価だった医療用アルコールを買ってきて自宅で酒造をしたりしていた。
- さらに、浜松の海岸で製塩をして、地元の人のお米と交換したりという気ままな生活だった。
40歳頃 本田宗一郎の個人事業として本田技術研究所を設立、「バタバタ」を製造・販売
- 1946年、宗一郎は旧友の自宅を訪ね、旧陸軍で使っていた、小型の発電用エンジンを見つけた。それを見て、宗一郎は、当時の生活の足であった自転車にこれをつければ、人々の移動や、物を運ぶことを、楽にできると考えた。
- 宗一郎は早速制作に取り掛かり、自宅で使用していた湯たんぽも活用しながら、第一号を制作した。妻さちに浜松駅前で試乗してもらったところ、周囲から大変好評を得た。宗一郎は、仕事へのやる気を取り戻し、浜松市内に本田技術研究所を設立した。
- 戦後で、軍が使用していた通信機用の旧陸軍六号無線機用小型エンジンが安く出回っていたため、それらを買い集めて量産を始めたが、全国から注文が殺到し、生産が追い付かなくなった。
- そこで宗一郎は、エンジンも自作することを決意し、設計を開始。この頃、初の学卒社員となる河島喜好(のち2代目社長)が入社し、エンジンの開発を手伝っていた。1947年には、本田初のA型エンジンという、ベルト電動式のエンジンの開発に成功し、量産を始めた。これは飛ぶように売れ、事業が軌道に乗り始めた。

出典:本田技研工業
42歳頃 本田技研工業株式会社を設立
- A型エンジンが飛ぶように売れたため、宗一郎は個人事業として行っていた本田技術研究所を法人化し、本田技研興業株式会社を設立した。資本金は100万円、従業員は34名だった。A型に加え、オート3輪用のB型、A型と同じく自転車補助用のC型を製造・販売していた。

出典:本田技研工業
オートバイメーカーとなる挑戦の時代
43歳頃 初のオートバイ「ドリームD号」を販売
- エンジンを販売しているうちに、宗一郎の中に次第にオートバイそのものを作りたい気持ちが芽生え始めていた。
- そこで、D型エンジンが開発されたときに、車体そのものに付けてオートバイを製造・販売し始めた。スピードに夢を託すという意味を込めて、「ドリームD号」と名付けられたこのモデルは、当初順調に売れた。
43歳頃 藤澤武夫との出会い
- しかし、景気が悪化し、「ドリームD号」の売れ行きが悪化したり、オートバイを売った相手から売掛金を回収する前に倒産してしまったりしたことで、本田技研工業の資金繰りは悪化していった。資金繰りに困窮した宗一郎は、通産省に勤めていた竹島弘(のち常務)の紹介で、藤澤武夫と会うこととなった。
- 藤澤は宗一郎より4年年下で、1910年に東京の小石川に生まれた。父秀四郎は広告会社を経営していたが、関東大震災を契機に倒産してしまい、藤澤は家族を養うために教師になる夢を諦め、宛名を書く筆耕屋などをやっていた。
- その後、鉄鋼の販売員として活躍し、1939年には自ら会社を起こし、切削工具の制作を開始し、戦後は製材業も営んでいた。
- 宗一郎は藤澤と会ってすぐに藤澤を気に入り、提携を固く約束した。藤澤もまた宗一郎のことを気に入り、出会いから2か月後には自らが経営する製材所を畳み、常務取締役として本田技研工業に入社した。

出典:本田技研工業
「私は東海精機時代はもちろん、それ以前から自分と同じ性格の人間とは組まないという信念を持っていた。自分と同じなら二人は必要ない。自分一人でじゅうぶんだ。目的は一つでも、そこへたどりつく方法としては人それぞれの個性、異なった持ち味をいかしていくのがいい、だから自分と同じ性格の者とでなくいろいろな性格、能力の人といっしょにやっていきたいという考えを一貫して持っている」
(本田宗一郎(2001)「本田宗一郎 夢を力に」日本経済新聞出版社)
「藤澤という人間に初めて会ってみて私はこれはすばらしいと思った。戦時中バイト(切削工具の刃)をつくっていたとはいいながら機械についてはズブのしろうと同様だが、こと販売に関しては、すばらしい腕の持ち主だった。つまり私の持っていないものを持っている。私は一回会っただけで提携を固く約束した」
(本田宗一郎(2001)「本田宗一郎 夢を力に」日本経済新聞出版社)
44歳頃 東京に進出、ヒット商品を次々生み出す
- 藤澤を常務に迎えた宗一郎は、東京の京橋に営業所を設立した。そこでは、藤澤が営業所を拠点に関東、甲信越、東北の営業を行った。宗一郎はすぐに北区上十条に組み立て工場も作り、東京へ進出した。東京に進出したのは、田舎に住んでいては製品のデザインも田舎くさくなるということに加え、周囲の目が気にならない都会で生活したいという思いもあった。
- 東京に来て間もなく、宗一郎は4ストロークの2輪である「ドリーム号E型」と、自転車に取り付けるエンジンである「カブF型」を発売し、ヒットさせた。供給能力が不足したため、東京進出から2年目で早くも埼玉県白子(現和光市)に工場を設立し稼働させたが、こちらもすぐに供給能力がひっ迫するほど、全国から注文が殺到した。
46歳頃 小型モーターの開発により、藍綬褒章を受章
- 1952年、宗一郎はそれまでの150件以上の特許に対し、藍綬褒章を贈られた。受賞者はモーニングで礼装するのが通常だが、宗一郎は普通のスーツさえ持っていなかったため当初はツナギで行くと答えていた。しかし通産省から着用のお願いがあったため宗一郎は藤澤が用意したモーニングを着て出席した。
48歳頃 経営危機、そしてマン島TTレースへの出場宣言
- 1952年、宗一郎はアメリカ、河島が欧州を訪れ、組み立てだけでなく生産の強化を図るべく、大型の設備を購入した。当時のホンダは売上が24億円、資本金600万円だったが、設備は4億5千万円だった。
- 後年宗一郎はこの生産設備導入を自分が行った一番の英断だったと振り返っているが、その支払いは本田技研工業にとって重い負担となった。
- 日本全体が不況に苦しむ中、本田技研工業の複数の主力商品がクレームや販売不振にあってしまう中、これまで順調に進んでいた経営に一気に不安定になった。藤澤はまず代金回収の早期化に取り組むと、労働組合との調整、資金調達に奔走し、なんとか経営危機を乗り切った。
- 経営危機の中、宗一郎は英国のマン島TTレースという、二輪の世界最高峰の大会に出場することを宣言し周囲を困惑させた。マン島TTレースは宗一郎の子供のころからの夢であったとともに、世界最高の技術を手に入れるための機会であり、世界にホンダの二輪を知らしめるための機会だと考えていた。
- 1954年、宗一郎は早速英国に渡りマン島レースを観戦したが、自社で作っている二輪の3倍もの馬力を持つ二輪が走っている姿を見て、衝撃を受けた。しかし帰国後すぐに研究部を立ち上げ、苦心の結果1959年に初出場し6位という好成績を残し、1961年にはついにTTのグランプリレースに優勝し、世界一を達成してしまった。
52歳頃 スーパーカブを発売
- マン島TTレース視察も兼ねた欧州出張から帰ってきた宗一郎は、レース用だけでなく、一般販売用にも二輪を開発していた。それが往年の名車、スーパーカブであった。1年8か月の開発期間をかけ、「そば屋の出前持ちが片手で乗れるクルマにする」というコンセプトで作られた二輪は、クラッチがなく、片手運転も可能だった。それまで二輪に乗ったことがなかった人びともスーパーカブを欲しがり、あっという間に注文が殺到し、ベストセラーとなった。

出所:本田技研工業株式会社
四輪メーカとなる挑戦の時代
57歳頃 四輪事業に参入
- 1955年、日本政府が国民車育成構想を打ち上げると、宗一郎は1958年に社内に四輪開発の部署を立ち上げた。開発チームは当初、政府の構想に沿った軽四輪車を開発していたが、補助金を貰って他社と同じ製品を作るより、スポーツカーを作ったほうがいいという宗一郎の意向により、途中からスポーツカーの開発に切り替えた。また、時を同じくして、藤澤からは今後の市場ニーズと本田技研工業の実力を考慮した結果、軽四輪トラックの商品化の指示が飛び、開発チームは二つのモデルを開発することとなった。
- ところが、1961年、通産省は、国内産業の競争力強化のため、国内メーカーを3つのグループに整理統合し、新規参入を規制する方針を打ち出した。それまで開発を行ってはいたものの、急ぎ自動車製造の実績を作らなければならなくなった。そうして1962年、本田技研工業はスポーツカーのT360と軽四輪トラックのS500を発売した。宗一郎は57歳にしてようやく四輪事業に参入したのであった。

出典:本田技研工業
59歳頃 F1に出場
- 1964年、宗一郎はF1への出場を宣言する。レースをすることで四輪車の性能が向上するという信念から来る決断だった。スポーツカーと軽四輪トラックを発売したばかりのホンダが世界最高峰の四輪車レースに出場することは、常識では考えられないことだった。しかし宗一郎は出場するからには勝つことを目標とし、研究所では宗一郎自らが床に座ってチョークで図面を書きながら開発を進めた。
- 当初、シャーシを提供してくれるはずだった欧州メーカーから供給を断られ、自社開発せざるを得なくなるなどのトラブルに見舞われながらも、なんとか車体は完成した。そうして本田技研工業は1964年8月のF1に出場し、惨敗を喫した。
- しかしこの惨敗を契機に開発チームが奮起し、翌1965年のメキシコ・グランプリでは優勝を遂げた。二輪だけでなく、四輪でもホンダは世界一のクルマを作ったことが証明された瞬間だった。
64歳頃 名車シビックを発売
- 1972年、宗一郎は4ドア、1500ccの本格的な小型乗用車「シビック」を発売した。翌年にはCVCCエンジンを搭載し、1973年度のカーオブザイヤーにも選ばれ、大ヒット商品となった。日本だけでなく米国でもヒットし、歴史に残る名車となった。米国では、発売から4年連続で、燃費第1位のクルマの称号も獲得しており、二輪だけでなく四輪でもホンダはアメリカでのブランドを植え付けることに成功した。
引退
65歳頃 盟友・藤澤と共に引退
- 1973年、創業期から経営を共に担ってきた藤澤は、後進が育ってきたことと、宗一郎というカリスマに頼った経営の限界を察知し、25年という節目のこの年に辞めることを決断した。藤澤の辞意を西田専務から聞いた宗一郎は、すぐに藤澤と共に辞めることを決意し、同年10月の株主総会で藤澤と共に正式に退任した。宗一郎が65歳、藤澤が61歳、後任社長の河島が45歳という若さだった。「さわやかなバトンタッチ」「潔い出処進退」とマスコミははやし立てた。25年間、ホンダという新興企業を世界のホンダへと大きく育てた宗一郎と藤澤は、引き際までも見事であった。

出典:本田技研工業
84歳頃 肝不全のため死去
- 1991年、宗一郎は癌治療のため入院していたが、肝不全により死去した。生前から「敬虔な無神論者」を公言し、葬式を開くことにより起こる交通渋滞を懸念した宗一郎の意向により、社葬は行われなかった。しかし社葬に代わる「お礼の会」が本田の各拠点で開かれ、のべ6万人以上が参加した。
「生きているから本田宗一郎は偉いとかなんとか、世の中は言ってくれる。死んでしまえば犬も猫も人間も同じようなものだ。おら、死んだら生きてる連中に迷惑かけるから葬式はやっちゃいけねぇ、って言ってるんだ。だって葬儀に来るヤツはクルマに乗ってくるんだろ。どう考えたって近所は交通マヒだよ。クルマ屋のオヤジとすりゃ、こんなことやっちゃいけねぇ。」
(梶原一明(2009)「一冊でわかる!本田宗一郎」PHP研究所)